※こちらは前半です※
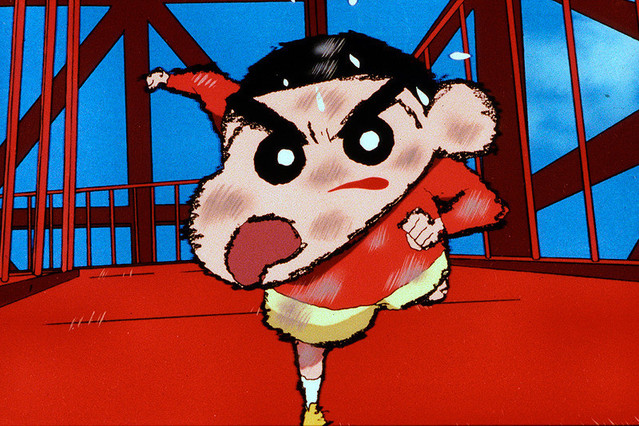
クレヨンしんちゃんは今まで数多くの映画が公開されたが、2001年に封切られた『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲』、通称『オトナ帝国』は、最高傑作との呼び声も高い。他にも『戦国大合戦』『ロボとーちゃん』など名作はたくさんあるが、個人的に本作が最も印象深い。
子ども向けといいながら、これほど風刺的で痛快な作品は今までに類を見ない。今回、私はコロナ禍で息苦しい社会を、『オトナ帝国』を通じて見ていきたい。
その際、前半と後半に分けてまとめる。前後半で関連する内容が多いので、どちらもご覧になってくれれば筆者は泣いて喜びます。(巧妙なステマ)
また、この考察は作品の内容に関するものよりも、『オトナ帝国』と現代社会に通底する風潮や現象を優先して見ていこうと思う。
あらすじ
子ども時代を追体験できる”20世紀博”に、すっかり夢中になるひろし・みさえら大人たち。彼らは子どものように豹変し、20世紀博へ連行されてしまう。取り残されたしんのすけらかすかべ防衛隊は、彼らを奪還すべくそこへ向かう・・・。
考察
昔はよかった
懐古する言葉としてよく使われる「昔はよかった」。1990年代~2000年代の「就職氷河期」・「失われた10年」・「ロストジェネレーション」、すなわち本作が公開された2001年周辺を、この言葉が象徴する。
高度経済成長やバブルで輝かしく成長する日本。未来は明るい、そう思われていた。しかし、現実は非情だ。バブル崩壊後に慢性的な経済停滞や政治不信が襲い、90年代以降は「就職氷河期」やら「失われた10年」やら、若者は「キレる17歳」と散々な言われ様。
高度経済成長やバブルを生きた人々の目には、この時代はむなしく映る。夢も希望も金もない。時代の被害者となった彼らの生き様は、華やかな過去を偲ぶことであった。
バブル崩壊後、当たり前が当たり前でなくなった日本社会。人間は変化を嫌う生き物である。今までの馴染み深い生活からの脱却を余儀なくされるも、それを懐かしく思うのは当然である。

現在のコロナ禍の社会も同様だ。時短やらソーシャルディスタンスやら慣れない自粛生活に閉口し、コロナ以前の生活に戻りたいと思うはずだ。
「昔はよかった」それは現実逃避する魔法の言葉。だが、この魔法は現実という空気を吸えばすぐに解ける。
しかし、『オトナ帝国』ではそうではない。本作で登場する20世紀博は、それを具現化して実際に手に触れさせることで、永遠に現実逃避を暗示することができる。
例えば、野原ひろし・みさえは家庭を支えるために、日々奮闘する。しかし、20世紀博を訪れた彼らは現実を忘れ、思い出に没頭する。だって、先の見えない努力より楽しい過去の追体験の方が、ずっと気楽なんだもの。
20世紀博を完成させたケン曰く、そこの中には「懐かしい匂い」が充満しているという。もし現実でも20世紀博のような施設が存在すれば、今の人々は病膏肓に入ったように熱中するに違いない。多分私もハマる。
(命名すれば、”人の温もり万博”? 風俗みたい……)
世代間の相克
一方で、『オトナ帝国』で見捨てられたのは子どもたち、換言すれば輝かしい日本を知らない世代である。 大人たちは子どもたちを冷たくあしらい、21世紀博へと姿を消した。大人のコミュニティと子どものコミュニティが、物理的・精神的に乖離した状態となった。
このような年齢による社会の分断は、何も創作の世界にとどまらない。現実でも、度々社会が年齢で分断されていると、私は感じる。
バブル崩壊の場合
少々話は脱線するが、面白い事例を出そう。就職氷河期世代であった赤木智弘氏は、フリーターとして働いていた。2007年『論座』に寄稿した記事で、彼は一躍脚光を浴びることとなる。以下、その引用である。
バブル崩壊以降に社会に出ざるを得なかった私たち世代(以下、ポストバブル世代)の多くは、これからも屈辱を味わいながら生きていくことになるだろう。一方、経済成長著しい時代に生きた世代(以下、経済成長世代)の多くは、我々にバブルの後始末を押しつけ、これからもぬくぬくと生きていくのだろう。なるほど、これが「平和な社会」か、と嫌みのひとつも言いたくなってくる*1。
うーん、何とも過激な題名に過激な文章。これは言うまでもなく大論争を惹起し、特に左派陣営からの批判を呼んだが、新進気鋭の新人はすぐさまこう反論する。
なぜバブルの恩恵を受けた人間が焼け太り、我々のように何の責任もないはずの人間が、不利益だけを受容しなければならないのか。左派の理論はそうした疑問に答えてくれない*2。
所得の低いポストバブル世代を利用するだけの左派は、実際に解決する姿勢を見せていないと赤木氏は主張する。ただし、彼が「左派に絶望しつつも、決して右傾化するつもりはない*3」と釘を刺していることは留意してほしい。
この主張は既存の論壇から手厳しく批判された一方で、若者から一定の支持を得たことも事実だ。ただ、私が言いたいのは、彼の主張の賛否ではない。バブル崩壊という歴史的な出来事が、このような世代の分断を生んでいることである。
コロナの場合
学校が休校になり、部活動やサークル活動、就職活動がままならない若者。「若者が感染を広げている」「若者の外出を止めるべき!」と吹聴するメディアや政治家。(ここで政策の是非を問うつもりはないが)
一方で、高齢者偏重の政策に嫌気がさした若年層は、「高齢者も自粛しろ」と老年層に批判の矛先が向き、「老人はコロナで淘汰されるべきだ!」という過激な主張までも見受けられる。この現象は日本に限ったものではなく、欧米ではboomer(日本の団塊の世代)を批判する『#boomerremover』というハッシュタグが話題になった*4。
(Twitterでこれらを探そうと思ったが、気が病みそうなのでご勘弁……)
理解できない他の世代に対して互いに攻撃を展開し、自身の溜飲を下げる。この風潮を正当化するつもりは毛頭ないが、当然の帰結にも思える。バブル崩壊といいコロナといい、世代間の対立はいつの時代も潜在的に起こっていて、歴史のターニングポイントがそれを顕在化させたにすぎない。
『オトナ帝国』では20世紀博の存在が分断を招いたが、現実ではそれがバブル崩壊やコロナに置き換わる。

まとめ
『オトナ帝国』と現代社会で共通する現象を、今一度まとめてみよう。
① 人々は懐古したい心を持っている
② 世代間の分裂の露呈
生活様式や価値観が変容すれば、我々は以前のそれを懐かしむ。ケンや恋人のチャコはその感情を基に21世紀博を完成させ、共鳴した大人たちはそこに足しげく通った。また、20世紀博の誕生や現実ではバブル崩壊やコロナなど、社会的にマイナスな出来事が起これば、鬱憤・怒り・ルサンチマン等によって世代間の分裂が往々にして活発化する。
本作は社会を鋭く観察し、それを明確に描かれていると驚嘆するばかりである。
後半に向けて
さて、キリも良くなったので一旦ここで区切りたい。
正直行き当たりばったりな解説が多くて反省点は数知れないが、最後までご覧いただいて嬉しい限りだ。
後半は、我々の将来、いわゆるポストコロナについて見ていこう。未来の生活様式や社会、価値観はどうなってゆくのか。『オトナ帝国』にヒントが必ず隠されているに違いない。それを後半で解き明かしてみたい。
忌憚のないご意見を是非ともお寄せください。
それでは👋